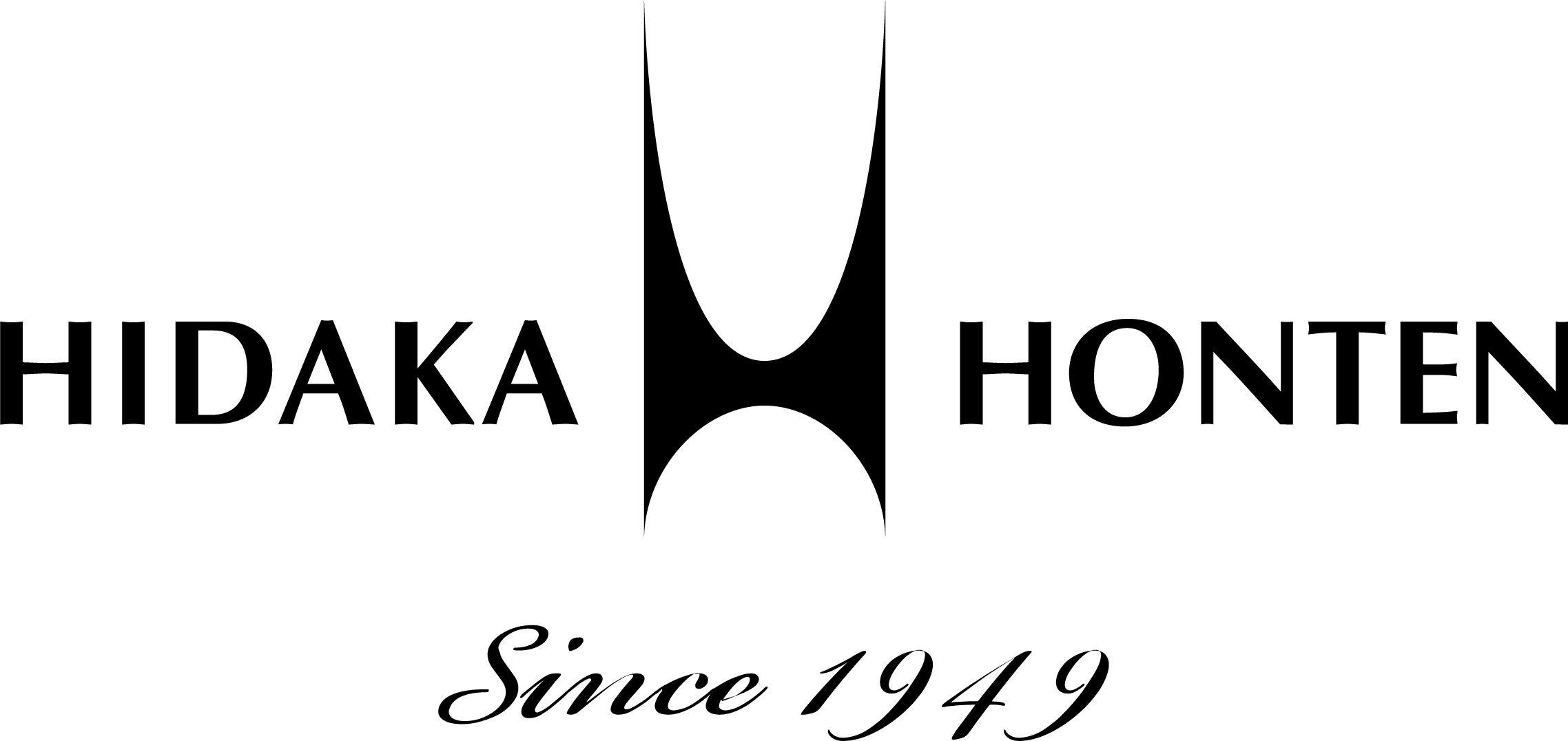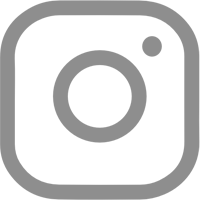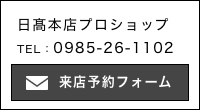1日は24時間で1,440分の86,400秒
お久しぶりです。
日髙です。
昨日5月20日は「世界計量記念日」でしたが、
皆さん、この記念日のことをご存知でしたか。
1875年5月20日に、欧米17ヵ国間で「メートル条約」が結ばれました。
この「メートル条約」は世界的な度量衡の統一を目的としており、
メートル法が国際的に採用されたことで、
標準化された測定単位が確立されたのです。
「メートル条約」締結の125周年を記念し、1999年「世界計量記念日」として制定、
翌年の2000年から実施されているそうです。
さて、本日のポイントは「世界的に標準化された測定単位」の確立。
すべてのものに対して「世界的に標準化された測定単位」が存在しますが、
私からは時計にまつわるものについてお話したいと思います。
時計にもいくつか不可欠な「世界的に標準化された測定単位」がありますが、
その中でも”1秒”という単位が非常に重要になってきます。
そして、単純に”1秒”といっても、原子時計、電池式時計、機械式時計において
それぞれ全く異なる仕組みで設定されていて興味深いです。
原子時計では、セシウム(Cs)という原子の共鳴周波数の
”9,192,631,770Hz” が1秒の基準になっています。
これを利用して、なんと7000万年に1秒しかズレないという
極めて高い精度が計測できています。
先日話題になった、1台5億円で受注開始された光格子時計のニュースで
原子時計を知った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
電池式時計だと、水晶の振動を利用して1秒を測っています。
これは水晶の特徴である、電圧を加えると正確に 32,768回振動することを利用しています。
電池式時計の精度はひと月にどのくらいズレるか”月差”という単位で表され、
一般的なものだとプラスマイナス10秒から20秒といわれています。
機械式時計でも、振動を利用することは同じです。
振動数を計測する対象は”てんぷ” という部品で、これが1秒間に振れた数を計っています。
8振動や10振動というワードを耳にしたことがあると思いますが、それが振動数です。
現在の主流は8振動/秒 ( 28,800振動/時 ) で、
高精度のものになると、10振動/秒 ( 36,000振動/時 )
いわゆるハイビートと呼ばれるものになっていきます。
振動数が高くなるにつれて精度も高くなっていきますが、
一方で部品の消耗が激しくなる特徴があります。
少々マニアックな箇所になりますが、
各社の代表的なムーブメントの振動数を調べてみました。
| ブランド | ムーブメント | 振動数 | 主な搭載モデル |
| ブライトリング | B01 | 8振動/秒 (28,800振動/時) | ナビタイマー、クロノマットなど |
| オメガ | キャリバー3861 | 6振動/秒 (21,600振動/時) | スピードマスタープロフェッショナル |
| グランドセイコー | 9SA5 | 10振動/秒 (36,000振動/時) | SLGH005(白樺モデル) |

↑ブライトリング B01

↑オメガ キャリバー3861

↑グランドセイコー 9SA5
こう見てみると各ブランド違っていて興味深いですよね。
もっと深く調べて、またおもしろい話題があったら共有します!
今回は単位について書かせていただきました。
いつものブログと比べると文章量が多いですが、
ぜひお時間のある際に読んでいただけたら嬉しいです。
※ 本日は水曜日のため、日髙本店・日髙本店プロショップ両店ともに店休日となります。
本日のひと:日髙颯見(日髙本店プロショップ 勤務)
===========================
日髙本店プロショップ
TEL 0985-26-1102
mail h-info@hidakahonten.jp
※2022年6月より毎週水曜日は定休日となります。
(水曜日が祝日の場合、前日の火曜日が定休となります)
日髙本店プロショップインスタグラムはこちら。

※「来店予約」をご利用の方はこちらのフォームから。