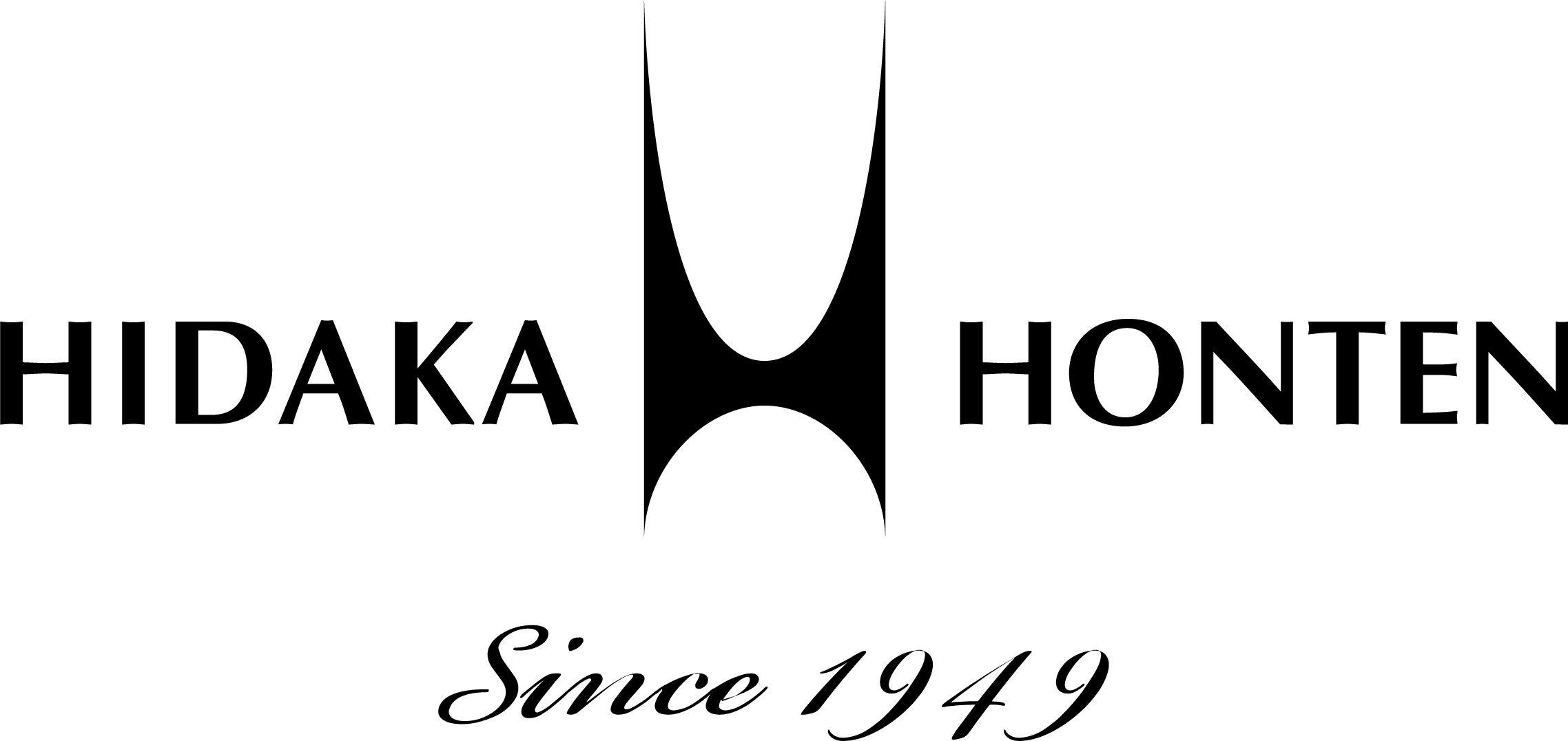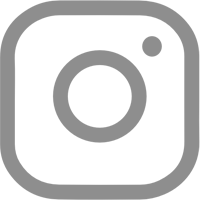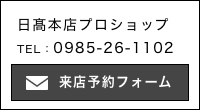子守歌の里を目指して
今回は、一般道でドライブしながら目的地を目指しました!
天気の良い山道を登り約2時間35分で『道の駅 子守唄の里 五木』に到着。

ここには、豆腐類やくねぶ(柑橘系果物)が多く販売されていました。
試しに、豆乳と、くねぶドーナツを購入して食しましたが、
豆乳は素材そのままの味で、自分の舌には自然派過ぎたみたいです。
くねぶドーナツは、美味しく頂きました!

しばらくゆっくりして、近くの川沿いのお店に行こうとしたら、
橋の上からバンジージャンプするのが見えました!

帰りには、『道の駅 人吉』でお土産を、
小林の『百笑村』でシャインマスカットや梨を、
『道の駅 ゆーばるのじり』では銀杏を、
野尻の『希望の店』で焼き鳥を購入しました。
(改めて書き出すと、結構色々なものを買いながら帰っていました・・・)


ここで、私の便利ツール『ウィキペディア』で、『五木の子守歌』を検索してみると…
五木の子守唄(いつきのこもりうた)は、熊本県球磨郡五木村に伝わる子守唄である。
子守唄には子守女がみずからの貧しく恵まれない薄幸な境遇(年貢代わりに働かされる)を嘆き、
悲しい日々の生活心情を基盤に,この種の子守唄は伝承されてきている。
第2次大戦後レコードに吹き込まれてから大流行したが,
地元のものとはやや曲節の違ったものになっている。
現在では熊本県を代表する民謡としても知られる。
日本の民謡や童歌などで、「子守唄」とされる歌には、
本来の童話(子供を寝かしつけるための歌)と、
守り子唄(もりこうた)と呼ばれる唄とがあるといわれており、
五木の子守唄は、守り子唄のひとつである。
守り子唄とは、子守をする少女が、自分の不幸な境遇などを歌詞に織り込んで
子供に唄って聴かせ、自らを慰めるために歌った歌である。
かつて子守の少女たちは、家が貧しいために、「口減らし」のために、
預けられることが多かったという。
歌詞には「おどま勧進勧進」という言葉が出てくる。
「おどま かんじん かんじん あん人たちゃ よかしゅ よかしゃ よかおび よかきもん」
ここに出てくる「かんじん」とは、
「三十三人衆」と呼ばれる地主層に対しての「勧進」(小作人)という意味で、
ここでは「物乞い」「乞食」という意味で用いられている。
歌の意味は「私は乞食のようなものだ。
(それにくらべて)あの人たちは良か衆(お金持ち、旦那衆)で、
良い帯を締めて立派な着物を着ている」となる。
伝承によれば、治承・寿永の乱(源平合戦)に敗れた平氏一族が五家荘(八代市)に定着したので、
鎌倉幕府は梶原氏や土肥氏など東国の武士を送って隣の五木村に住まわせ、
平氏の動向を監視させたという。
その後、これら武士の子孫を中心として「三十三人衆」と呼ばれる地主層が形成され、
「かんじん」と呼ばれた小作人(名子小作)たちは田畑はもちろん、
家屋敷から農具に至るまで旦那衆から借り受けて生計を立てなくてはならなかった。
娘たちも10歳になると、地主の家や他村へ子守奉公に出された。
五木の子守唄はこの悲哀を歌ったものである。
五木の子守歌、聞いたことはありましたが、このような意味がある唄だったのですね。
昔世代の自分は、西都市の三財生まれです。
凄く田舎で、当時家の周り2キロ以内に信号は無かったです。
井戸から水をくんでいたし、トイレとお風呂は別棟でした。
そんな住まいだったので、五木の子守唄を聞くと、当時が思い出されます。
昔を思い出させてくれた場所に感謝して、これからも良い思い出を探しに行きたいと思います。
それでは、良い2025年11月をお過ごし下さい。
本日のひと:緒方(日髙本店プロショップ 勤務)
===========================
日髙本店プロショップ
TEL 0985-26-1102
mail h-info@hidakahonten.jp
※2022年6月より毎週水曜日は定休日となります。
(水曜日が祝日の場合、前日の火曜日が定休となります)
日髙本店プロショップインスタグラムはこちら。

※「来店予約」をご利用の方はこちらのフォームから。